戦略MQ会計講座

利益が見える戦略MQ会計(かんき出版)
の著者が伝える「MQ会計と直接原価講座」
MQ会計と直接原価(ダイレクトコスティング)
カツ丼1杯の原価

1杯800円で提供しているカツ丼の原価について考えてみましょう。
わかりやすいように、この食堂ではカツ丼しか売っていないものとします。食堂の店主が計算しているカツ丼1杯の原価はご飯、豚肉、パン粉、たまねぎ、たまごなどの「どんぶりの中身(食材)です。
ところが1杯800円のカツ丼が1個800円の機械部品になった途端にどうなるでしょうか。製造業では製品の製造原価(材料費+労務費+製造経費)を求めようとします。これが「FC全部原価(フルコスティング)」です。
日本の製造業や建設業では、FC全部原価で製品や工事の原価計算を行っています。
つまり、掛かった材料費と外注費に手間賃(労務費)と経費(製造経費)を上乗せする計算方法です。

ここでカツ丼を機械部品とみなして原価を計算してみます。
カツ丼1杯800円の材料費は300円、これに作る人の手間賃(労務費)と経費(製造経費)を加えてみます。
月給50万円の店主が1か月25日8時間働くとして、
1分当たりの人件費は41.67円(50万円÷25日÷8時間÷60分)。
カツ丼を1杯作るのに15分かかるとすると労務費は625円(41.67円×15分)。
このほかに水道光熱費、設備の償却費などの経費が80円かかったとすると、カツ丼1杯の原価は次のように計算されます。
カツ丼1杯の原価:材料費300円+労務費625円+経費80円=1005円

これでは売れば売るほど赤字になってしまいます。
原価を下げるために月給20万円の社員にカツ丼を作らせることにしました。ただし時間は20分を要します。
労務費は333円(20万円÷25日÷8時間÷60分×20分)となり、これでやっと800円で売っても利益が出るようになりました。
カツ丼1杯の原価:材料費300円+労務費333円+経費80円=713円
労務費や経費を個別に計算するのは手間がかかります。
そこで全体の目安として製造にかかる労務費と経費のレートをあらかじめ決めておく方法が賃率や分単価です。建設業では、間接経費を現場ごとに配賦するという処理を行います。
製造業や建設業ではこのようにして製品や工事ごとの原価計算を行っています。
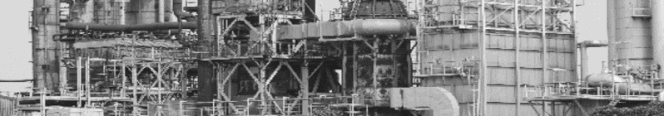
製造業や建設業における原価計算については、税法で細かく規定されています。
じつはこれが、この先の経営を考えるうえで大きな障害になってくるのです。
さらに、FC全部原価では
「期末あるいは月末の製品在庫が多ければ多いほど(作れば作るほど)利益が出る」
というおかしな現象が発生します。
カツ丼(製品)は売れてはじめて利益が出ますが、カツ丼を作って店頭に並べるだけで利益が出てしまうのです。
DC直接原価で考える
もし街の食堂がFC全部原価でカツ丼の原価計算を始めたら
月給50万円の店主が作るカツ丼は800円では売りません。
原価1005円のカツ丼は、売れば売るほど損をしてしまうからです。
したがって、このような原価計算を行っている製造業では、
赤字になってしまうこの機械部品を800円では受注しません。
ところが街の食堂では、月給50万円の店主が作るカツ丼を
1杯800円で売っても潰れません。

MQ会計では、カツ丼1杯の原価Vはどんぶりの中身、つまり米、卵、豚肉などの材料費のみです。
重要なのは1日に何杯(Q)のカツ丼が売れるかです。
「お客が何人来たのですか?」 です。
このように材料費や外注費のみを原価として計算する方法を
DC直接原価(ダイレクトコスティング)といいます。

FC全部原価で計算した利益をもとに経営分析をすると「まだ大丈夫!」という結果が出ますが、DC直接原価で計算すると「もっと売れ!」になってしまう場合が、往々にしてあります。そもそも、FC全部原価で作られた決算書からは、損益分岐点売上高は計算できないのです。
注)カツ丼の原価は説明をわかりやすくするためのもので、実際の原価とは異なります。
関連記事
⇒ 戦略MQ会計講座
